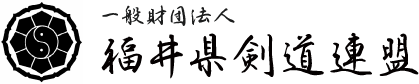最優秀賞 「中学生の部」に向井結衣さん(敦賀市剣道スポーツ少年団)、「小学生の部」に砂川亮太朗さん (九頭竜武徳館)
福井県剣道道場連盟は、剣道を通じて学んだことを作文で発表する「第48回中部地区剣道少年団研修会 福井県予選会 体験・実践発表会」を2025年10月31日(金)、敦賀市の「敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ」で開催しました。福井県剣道道場連盟加盟の各道場から小学生の部に5人、中学生の部に3人が発表、同連盟の奥井俊雄副会長ら8人が審査しました。
結果は次の通りです。
※小・中学生各最優秀賞1名は長野県剣道道場連盟主管で12月13日(土)に、長野県池田町の「池田町交流センター」で行われる「第48回中部地区剣道少年団研修会」で発表します。
▽小学生の部
最優秀賞 砂川亮太朗(九頭竜武徳館、森田小学校5年)
優秀賞 宮下倫太朗(豊神館、豊小学校6年)
優良賞 安富公紀(金井学園ジュニア剣道教室、社西小学校5年)
敢闘賞 奥井美月(敦賀剣道錬成館、南小学校5年)
敢闘賞 伊原碧人(敦賀市剣道スポーツ少年団、松原小学校6年)

△右から優秀賞の宮下倫太朗さん、最優秀賞の砂川亮太朗さん、優良賞の安富公紀さん

△体験・実践発表する最優秀賞の砂川亮太朗さん
▽中学生の部
最優秀賞 向井結衣(敦賀市剣道スポーツ少年団、松陵中学校2年)
優秀賞 河合浩義(金井学園ジュニア剣道教室、至民中学校1年)
優良賞 市村奏汰(豊神館、鯖江中学校1年)

△右から優秀賞の河合浩義さん、最優秀賞の向井結衣さん、優良賞の市村奏汰さん

△体験・実践発表する最優秀賞の向井結衣さん

△審査風景
■小学生の部 最優秀賞

九頭竜武徳館 森田小学校5年 砂川 亮太朗
剣道一直線
「始め」審判の、試合開始のかけ声とともに目の前の勝負に全力で挑む。120秒間集中する。1秒たりとも気を抜いてはいけない。「ヤー」腹の底から力いっぱい声を出す。相手にプレッシャーをかけ1本を取りにいく。今まで稽古してきた技を繰り出す。相手との攻防戦の末、一瞬のスキを見つけ、相手に有効打突を決める。その瞬間旗がいっせいに上がる。これがぼくの理想の戦い方だ。
ぼくは剣道が大好きだ。剣道を始めて約3年になる。始めた頃は、厳しい稽古で嫌になる時がよくあった。正直稽古へ行きたくなかった。毎回行く直前で「行きたくない。痛いし寒いしもう嫌だ」と泣いてしまい母を困らせた。母に励まされ、休まず毎日稽古に行く。そんな毎日をくり返しながら目の前の稽古を頑張ってきた。年度末に、道場の先生から皆勤賞の発表がある。そこで、なんと2年連続皆勤賞の表彰をされた。この表彰がぼくにとって転機となり、頑張れる糧となった。
剣道を通じて、勝負以外でも、様々なことで成長ができたように思う。
一つ目は、礼儀作法が身についたことだ。剣道は「礼に始まり、礼に終わる」という言葉があるように、礼儀が重視される競技だ。試合の勝敗とは別に、相手を尊重し、正しい礼の仕方から正座の仕方、挨拶の方法など重視されている。剣道を習うことで礼儀作法が自然と身に付き、正しく礼やあいさつができるようになった。学校の先生や近所の方、または病院へ受診した際も、「お願いします」「ありがとうございました」など、あいさつをしている。「大きな声であいさつしてくれていいね」「剣道をしている子は礼儀正しくていいね」とほめてもらう機会が増えた。剣道をしている子は誰しもが「礼儀正しい」と周りの人はとらえているのではないかとぼくは考えた。これは「礼に始まり、礼に終わる」という教えを守り続けてきた先人の剣士達のおかげではないだろうか。ぼくは一剣士として名が恥じぬようこれからも相手に対し礼儀を尽くすことをしていきたい。
二つ目は、コミュニケーション能力が身についたことだ。剣道は、他道場の先生に助言をもらうことも多く、様々な人とのコミュニケーションが必要となる。ぼくは、錬成会などで対戦した子に声をかけ、友達になることが多い。特に印象に残っている友達は、試合をした時、強くて自分にはかなわない相手だった。上下白の道着が格好よく、思わずその子に「友達になろう!」と声をかけた。「いいよ!」と快く言ってくれ、それからは、遠征先で会うたびに話す仲になった。県内外に友達ができ、今まで稽古をしてきたことを全力でぶつけてお互い試合をする。つらい錬成会でも、友達の道場が参加するとわくわくした気持ちになる。友達の力は大きい。
最後に、試合で負けてばかりで挫折したり、稽古で思うようにいかないこともある。「何が悪かったのか」「次にはどう活かすか」など日々模索する。竹刀の持ち方構え方、足さばき、打突までのすべてがつながっていることを意識し、自分自身の克服しなければならない点の原因を知り、稽古に取組むよう日々精進し明日へつなげる。そう考えられるようになったのは、剣道をすることによって、精神力や忍耐力が強くなったからだ。
ぼくの剣道人生はまだ始まったばかりだ。今後、つらいこと、苦しいことがでてくるだろう。その時は立ち止まって、次へ活かせるよう考え、理想の試合ができるように、一つ一つ地道に努力をする。また、新しい技や攻め方を研究し実戦につなげるよう試行錯誤する。これからもずっと「剣道一直線」挑戦することは楽しい。
一番の敵は、剣道をするときに現れる、すぐに気を抜いてしまう自分自身。いつかは気を抜いてしまう自分に勝ちたい。長い戦いになることだろう。自分自身に戦いを挑み続ける。己に打ち勝て。
「いざ、勝負!」
■中学生の部 最優秀賞

敦賀市剣道スポーツ少年団 松陵中学校2年 向井 結衣
私の剣道
保育園年中から始めた剣道は、早10年目になる。
中学校に進学してから、なかなか勝つことが出来ず、これまで稽古で積み重ねてきた自分の剣道が崩れていくような気がした。チームのみんなに迷惑をかけ、落ち込むこともあった。「このままではいけない」「これからは、どのような剣道を目指せばいいのか」なかなか良い答えは見つからなかった。
ある日、父が持っていた本を何の気なしに手にして読んでみた。「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」『もしドラ』といわれる小説本である。専門書や小説を読むのが苦手で、なかなか最後まで読むことの出来ない私だが、物語として楽しみながら最後まで読めた本である。2009年に発行された小説で、著者は岩崎夏海さんという方です。すごく可愛い名前なのでどんな方だろうとインターネット検索してみたら丸坊主のおじさんだった。
本のあらすじは、野球嫌いな主人公が、高校野球部の女子マネージャーをしていた親友が重病で入院してしまい、代わりを務めるべく女子マネージャーになる。やるからには目指すは一つ、野球部を甲子園に連れて行くこと!マネージャーの入門書を探していたが、間違ってドラッカーの『マネジメント』を購入してしまう。この『マネジメント』の本の内容は企業経営や組織論のビジネス書である。そのマネジメントの要素を高校野球に応用し、野球部を「顧客に感動を与える」組織と定義する。バラバラだった部員の心をひとつにして、各人の強みを活かし、マーケティングやイノベーションといった経営戦略を実践することで、チームを甲子園出場へと導いていく物語である。
『もしドラ』では、野球部における顧客を「応援者」ととらえ、応援者が応援したくなるようなチーム作りを目指しています。そこで、組織を成功に導くためのドラッカー理論の要素が具体的に描かれています。
一、真摯さ
組織に成果をあげさせることに、誰よりも執着する姿勢と解釈できます。
二、マーケティング
地域イベントや清掃活動など、地域住民と交流し、応援を呼びかけます。
三、イノベーション
部員の強みを活かし、新しいことにも挑戦することで、組織に改革をもたらそうとします。四、人材育成
個人の強みを最大限に発揮させ、責任を持たせることも重視されます。
野球と剣道、競技は違うけど、この本を読んだことで、私のこれからの剣道を見直すきっかけとなった。
私の剣道 マネジメント
一、全国大会出場を目標とし、全員で共有することを出発点とする。
二、目標達成のために技術向上、チームとしての戦略の計画を立てる。
三、顧客は選手であり、「剣道をやっていて楽しい。」「成長できた。」と感じられる環境づくりをする。
四、個人の弱みを補い、強みを最大限に引き出すチーム体制の構築をして、「試合で勝つための練習」という目的意識を持つ。
と考えた。与えられた使命や役割に真剣に向き合い、選手としてはもちろん全力で戦い、更にチームを勝利に導くようなマネジメントができたらと思っています。そして、剣の理法を修錬することで『正しい剣道』を追い求めていきたい。